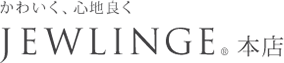江戸時代、現在の様な「下着」はありませんでした。
おりものや経血はどのようにして処理していたのか、気になったことありませんか?
今回は昔の日本人女性がどんな風に生理期間を過ごしていたかをまとめてみます。
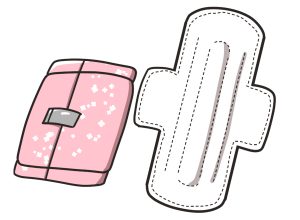
INDEX
腰巻が下着代わり。生理の時はどうしてた?
着物を着る時に、下に付ける「腰巻」をご存知ですか?巻きスカートの様に腰に巻いて装着するのですが、江戸時代の日本人女性は「腰巻」を下着代わりに身に着けていました。「湯文字」とも呼ばれています。
「湯文字」の由来は、銭湯などお風呂に入る時に使用していたから。大衆浴場などを利用する時には、専用の腰巻を付けて入浴しており、湯船に入って布が浮き上がらない様、鉛のおもりが縫い込まれていたそうですよ。
腰に巻くだけなので、ショーツの様にクロッチはありません。生理の時はふんどしを利用し、和紙の再生紙やぼろ布を挟んで吸収体として使用したり、丸めて膣の入り口にフタをするようにしていたんだとか。布は洗って再利用もしていたようです。また植物をすりつぶしたものを吸収体として使用することもあったそう。
明治、大正、昭和初期になると、「月経帯」と呼ばれる生理用の下着が出てきます。丁字帯と言うふんどしの様なものの股間を覆う部分に、吸収体である脱脂綿を挟んで使うものでした。
その後ズロース型の「月経帯」も普及します。半ズボン型のゆったりした形のもので、お腹までの長さのものは保温効果もあり人気だったそうです。
昭和38年(1961年)になると、アメリカから使い捨てナプキンが日本へ入ってきます。これで少し長い時間対応できる生理用品が出来ましたが、庶民にはまだまだ高価ものでした。まだ「月経帯」を使用する人も多かった様ですが、「月経帯」もショーツ型やパンティ型のものなど、より使用しやすいデザインが増えてきました。

こう考えると、日本での使い捨てナプキンの歴史は浅く約60年ほど。それ以前の日本人女性の生理期間中からは、苦労と工夫が感じられますね。
今と昔 女性の身体の変化
よく、昔の日本女性は、経血やおりものなどの量が現代女性よりも少なかったという話を耳にします。
なぜそういった話が広まっているのか、以下にまとめてみました。
【経血の量】昔の女性は月経血コントロールができていた
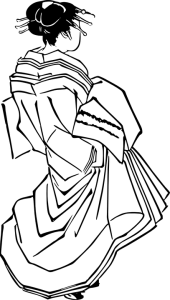
月経血コントロールとは?
月経血コントロールとは、簡単に言うと「経血をトイレで出す」。骨盤底筋を鍛え、経血の排出を膣を締めることで止めて、トイレに行った時に経血を出せるようにすること。
昔の女性は上記でお話ししたように、生理になった時は「膣の入り口に丸めた紙をフタの様に詰めたり、月経帯を使用」したりしていました。特に膣の入り口に紙を詰めるというのは、長時間持たなかったり、着ているものを汚してしまうこともたくさんあったでしょう。そこで経血が自然と出てこない様に膣口を締めるように意識し、トイレに行った際に、膣圧で紙と経血を出していた女性もいたんだとか。なんだかすごい話ですね!
現代の女性と比べて、畑仕事などの重労働で腹部の筋力があったとされる女性たちには、意識して膣口を締めるということが出来たと言われていますが、「膣に紙などでフタをして、トイレで一気に出していたという事」が、量が少なかった・あるいは生理期間が短かったという話につながるのでしょう。

特に、江戸時代などは「血は不浄なもの」とされており、生理期間中の女性は「月経小屋」という別棟に隔離されていました。コントロールしよう!という意識があったかはわかりませんが、その様な時代だったからこそ、着物を汚さない様に気を付けようという気持ちはあったのかも知れませんね。
【おりものの量】季節の食材と質素な食事で、健康的な身体が自然と保たれていた

皆さんはおりものがあるのは当たり前と思っていないかい?昔の女性はおりものなんて出なかったのよ。
引用:「子宮を温める健康法」若杉友子 著
このように語るのは、若杉友子さんという1937年生まれの女性。彼女は、現代の日本人の食生活を見直すことで、女性特有の不調が改善されると著書に記しています。
今の女性は、朝昼晩用と何種類ものナプキンを一日中使っているけれど、これは貧血、冷え性、低体温になるものばかりを食べているから、おりものと縁が切れないの。今はおりもの、昔は「こしけ」と言ったの。
こしけとは自然界の「時化」(しけ)のことを表していて、嵐で海が荒れているのと同じように、子宮の中が荒れて乱れていることを示しているんです。おりものには膣内の雑菌を洗い流す役目があり、おりものが多いということは子宮内に悪い菌が増えている証拠。本来女性の膣内は弱酸性で守られ、どんな病原菌も寄せ付けないといわれていますが、今は自浄力が弱まり、トリコモナス菌やガンジダ菌などのトラブル続きで通院している人も多いと聞きます。
動物性たんぱく質を食べ、砂糖を食べ、ナス科の野菜や果物を食べ、減塩しているから、血液が汚れおりものが降りて来るの。引用:「子宮を温める健康法」若杉友子 著
昔の食事は、米、野菜などが中心で、肉よりも魚を食べることが多く、さらにその風土に合った季節の食物を頂くという事は身体に良いと言われますから、冷えにくく自浄作用の強い身体になっていたのかもしれません。
現代の食事は、過度な動物性たんぱく質を摂っていたり、野菜や果物も季節関係なく食べられます。食べ物の他、服装、仕事など生活習慣も違いますから、このような生活習慣の変化が、女性のデリケートゾーンのお悩みにもつながり、今と昔ではおりものの量に違いがあると感じる理由なのでしょう。

月経血コントロールにしても、食生活にしても、現代女性にとっていきなり取り入れるのはなかなか難しいことです。また、昔の女性全てがそうだったとは言い切れませんし、経血やおりものの量が少ないから良い!ということではないですよね。
経血もおりものも、自分の身体を知るきっかけになるものです。量や色などの変化を観察し、病気など早期発見できるようにしたいですよね。
その上で、季節の食物を頂くことや、生理期間も快適に過ごせるように、生活習慣を改めるのが大切だと思います。

身体の不調を治すために、東洋・西洋医学、漢方など色々な手段がありますが、どれが自分に合うのかは試してみないとわからないことです。何を選択するのかは自分で決める事ですから、今感じている不調を治すために、まずは何をしたらいいか・手軽に始められるものは何なのかを調べてやってみるというのが良いと思います。
布ナプキンもそのひとつ。布ナプキンを使用する人の中には、「生理痛が軽くなった」「冷えが改善された」などと感じる方が多いですが、衛生面や洗濯などにデメリットを感じる方もいらっしゃいます。自分の生活スタイルに合わせて、無理をせず使うことが大切だと思います。
4つのテーマで比較!「紙ナプ」と「布ナプ」の違い
 使い捨てできる「紙」と肌に優しい「布」2種類を4つの共通テーマで比較しました!
使い捨てできる「紙」と肌に優しい「布」2種類を4つの共通テーマで比較しました!
【新規購入者様限定!お試し価格のおりもの用布ライナー】
 布ナプキンに興味があるけど…まだ使うのに不安があるという方は、ぜひこのおりものライナーから始めてみて下さい♪
布ナプキンに興味があるけど…まだ使うのに不安があるという方は、ぜひこのおりものライナーから始めてみて下さい♪